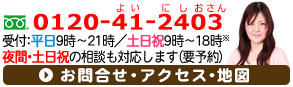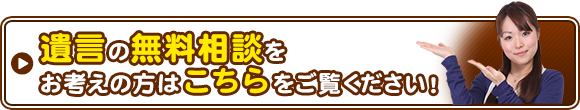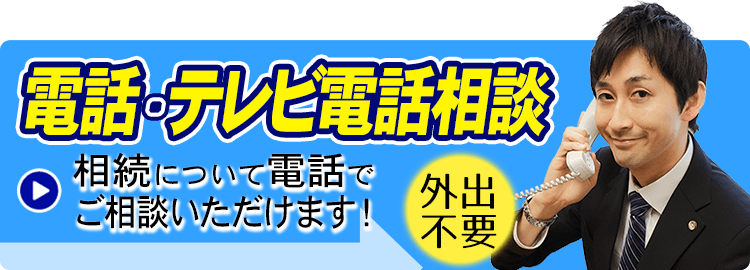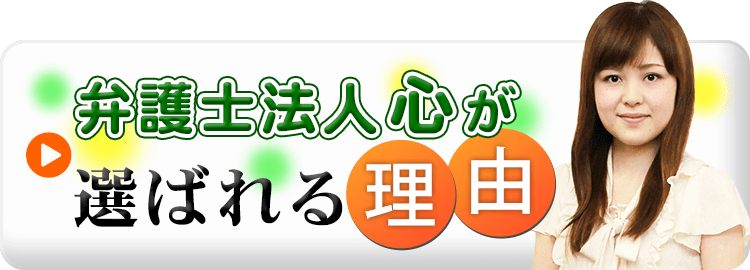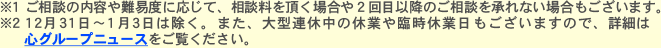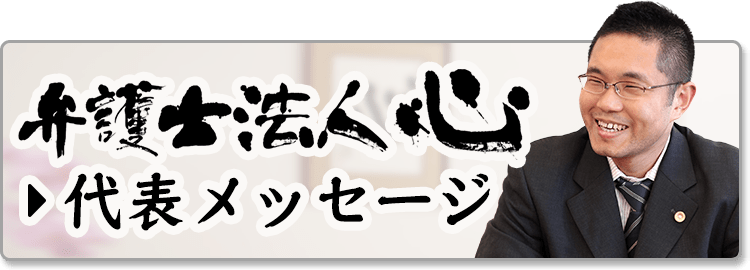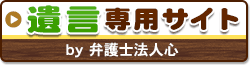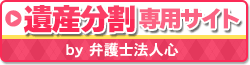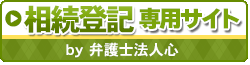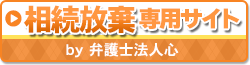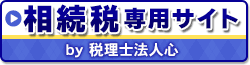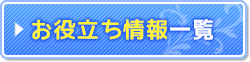遺言執行者が死亡した場合のQ&A
祖父が遺言を作成し、遺言執行者に父を指定していましたが、父が先に亡くなってしまいました。この場合、どうしたらよいのでしょうか?
遺言執行者が遺言の作成者(遺言者といいます)より先に死亡した場合、このままですと、相続が開始した後に遺言執行者がいない状態になってしまいます。
その場合、金融機関によっては、相続人全員の同意がないと預貯金の解約ができなくなる場合や、不動産の名義変更の手続きに相続人全員の同意が必要になる場合もあります。
そのため、遺言者としては、遺言書を書き直し、新たに遺言執行者を選んでおいた方が良いでしょう。
遺言者が認知症や病気等で新たに遺言執行者を選任することができない場合は、相続開始後に、遺言執行者の選任申立を裁判所に行う必要があります。
なお、公正証書遺言で遺言執行者を指定していた場合で、新たに遺言執行者を指定し直す場合は、公証人に新たな遺言執行者の氏名、生年月日、住所、職業を通知します。
この場合、新たな遺言書の書き直しのため、証人2人が必要になります。
遺言者の祖父が亡くなった後、遺言執行者の父が亡くなりました。この場合、遺言執行者を選任するにはどうすればよいのでしょうか?
遺言者が亡くなった後に、遺言執行者が亡くなった場合、遺言執行者がいないということになりますので、遺言執行者を選任するためには、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立を行う必要があります。
申立人は、相続人や受遺者等の利害関係人に限られます。
申し立てる先の裁判所は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
なお、遺言執行者の選任申立を行う場合は、弁護士などの専門家を遺言執行者として推薦することもできます。
一般的に、遺言執行者の選任申立を家庭裁判所に行ってから、1か月程度で遺言執行者が選ばれることが多いです。
また、遺言執行者と選ばれた人の報酬は、裁判所が決めます。
遺言執行者が先に亡くなってしまう場合に備えて、遺言書の書き方で工夫するところはありますか?
遺言執行者が遺言者より先に亡くなってしまう場合に備えて、予備的条項を入れておくことをおすすめします。
この場合の予備的条項とは、遺言執行者が先に亡くなった場合に備えて、あらかじめ次の遺言執行者を指定しておくというものです。
たとえば、遺言執行者の父が先に亡くなった場合は、孫が次の遺言執行者になると遺言書に書いておけば、この問題が解消されます。
また、別の方法としては、そもそも遺言執行者として専門家を指定しておくこともおすすめです。
もっとも、ここでも注意が必要な点として、遺言執行者として、個人の専門家をしてしまうと、当該専門家がなくなってしまえば、遺言執行者がいなくなってしまうことになる点です。
遺言執行者として、たとえば弁護士法人をしておけば、弁護士法人が存続する限り、遺言執行者が先に亡くなるといったことにはなりません。
相続税にも強い弁護士に相談すべき理由は何ですか? Q&Aトップへ戻る